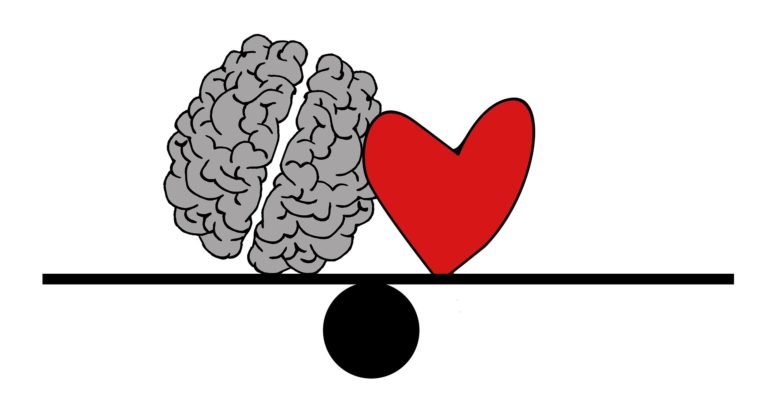「心がこもった挨拶」「心のこもったおもてなし」など心という言葉を使った表現はたくさんありますが、一般的には、胸や心臓を想像していることと思います。実は心とは、心臓や胸のことではありません。今回は、心とはどこにあるのか、そもそも心とはどういうものなのかについてお話します。
巷で言われている心とは実は脳のこと
心を痛めるや心が苦しいといったときに使われる「心」は実は脳のことを指します。心を痛める、心が苦しいということも脳が司令を出してそう感じていると言われています。
そのことから心を理解するには、脳の働きを理解することが大事になってきます。医学的にもまだ未知の世界が多い脳の働きですが、これから医学の進歩により少しずつ脳の働きが解明されることでしょう。
喜怒哀楽を司るのは「大脳辺縁系」
嬉しい、悲しいなど喜怒哀楽は、大脳辺縁系が関係していると言われています。特に「海馬」は記憶や空間学習能力において、扁桃体は情動学習(感情のさまざまな記憶)において重要な役割を担っています。
また、前頭連合野は、行動の自発性や計画性に関連しているので、前頭連合野が損傷すると、○○時に起きて、○○時に寝るといった行動ができなくなるばかりか、積極性や創造性がなくなったりします。
心と感情の関係性
感情は、さまざまなことを見たり聞いたりしたときに生じる気持ちのことです。犬が嫌いな人は、犬を見ただけで恐怖を感じますし、水が嫌いな人は、水を見ただけで息苦しくなります。
これらは、過去に「怖い思い」をしたときの恐怖が脳に焼き付いていて、反射的にそれらを避けて、身を守っています。同じものを見ても全く異なる感情が生まれるのはこうしたことも影響します。
身を守る感情もストレスになることも
過去の経験から反射的に身を守るのが感情というお話をしましたが、この感情が過度に働きすぎてしまうと、ストレスを作り出してしまうこともあります。
たとえば、先の犬の話で例えると、犬で怖い思いをした → 犬は怖いもの → 犬が襲ってくる という感じで、感情をもとにして、思考がネガティブな方向に向いてしまうケースです。
心も感情も脳の影響は大きい
今回は、心と脳の関係についてお話しました。
普段私達が口にしている「心」とは、実は脳のことをいい、脳からの司令で胸が苦しくなったり、気持ちがふさぎがちになったりすることが解明されています。
この心が持つ感情は、過去の経験が大きく影響します。そのため、経験の違いから同じものを見ても一方は喜び、一方は嫌悪感を抱くということが起きてしまいます。
これらは、経験の違いから生じているので、自分のことはもちろん相手のことを理解する上では、過去の経験を踏まえた感情も理解することも重要です。